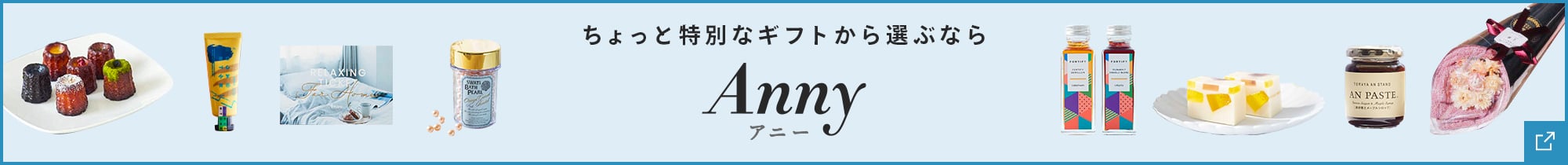- シーンから探す
-
贈る相手から探す
- 彼氏
- 彼女
- 男友達
- 女友達
- 夫・旦那
- 妻・奥さん
- お父さん・父
- お母さん・母
- 両親
- おじいちゃん・祖父
- おばあちゃん・祖母
- 女性
- 男性・メンズ
- 妊婦
- 同僚
- 同僚(男)
- 同僚(女)
- 上司(男)
- 上司(女)
- 部下
- ビジネスパートナー・取引先
- 夫婦
- カップル
- 親友
- 女の子
- 子供
- 男の子
- 赤ちゃん・ベビー
- 乳幼児
- 1歳の誕生日プレゼント
- 2歳の誕生日プレゼント
- 3歳の誕生日プレゼント
- 4歳の誕生日プレゼント
- 5歳の誕生日プレゼント
- 6歳の誕生日プレゼント
- 7歳の誕生日プレゼント
- 8歳の誕生日プレゼント
- 9歳の誕生日プレゼント
- 10歳の誕生日プレゼント
- 18歳の誕生日プレゼント
- 19歳の誕生日プレゼント
- 20歳の誕生日プレゼント
- 21歳の誕生日プレゼント
- 22歳の誕生日プレゼント
- 25歳の誕生日プレゼント
- 26歳の誕生日プレゼント
- 30歳の誕生日プレゼント
- 40歳の誕生日プレゼント
- 50歳の誕生日プレゼント
- 60歳の誕生日プレゼント
- 70歳の誕生日プレゼント
- 80歳の誕生日プレゼント
- 88歳の誕生日プレゼント
- 90歳の誕生日プレゼント
-
カテゴリから探す
- 名入れギフト
- 記念品
- 文房具
- 花
- ビューティー
- こだわりグルメ
- ジュース・ドリンク
- お酒
- 絶品スイーツ
- ケーキ
- お菓子
- プリン
- フルーツギフト
- リラックスグッズ
- アロマグッズ
- コスメ
- デパコス
- インテリア
- キッチン・食器
- グラス
- 家電
- ファッション
- アクセサリー
- バッグ・ファッション小物
- ブランド腕時計(メンズ)
- ブランド腕時計(レディース)
- ベビーグッズ
- キッズ・マタニティ
- カタログギフト
- 体験ギフト
- 旅行・チケット
- ダレスグギフト
- ペット・ペットグッズ
- 面白い
- 大人向けのプレゼント
- 贅沢なプレゼント
- その他ギフト
- プレゼント交換
- 絆ギフト券プロジェクト
- リモート接待・5000円以下
- リモート接待・8000円以下
- リモート接待・10000円以下
- リモート接待・10000円以上
- おまとめ注文・法人のお客様
茶道具 お茶会『博多曲げ物「炭斗(角)」在銘「玉樹」』(20,8㎝四方)未使用 無形文化財 茶事 表千家 裏千家 千家十職 七事式 茶懐石
-
商品説明・詳細
-
送料・お届け
商品情報
サイズは、208×208×高さ82㎝です。使用感は感じられますが、ほぼ未使用の状態です。美品です。炭斗は希少で、特注品だと思われます。 博多曲物(はかたまげもの) 博多曲物(はかたまげもの)とは、杉やヒノキの板を熱を加えて曲げて、それを桜の皮で綴じて作られるものです。関東では「まげわっぱ」と呼ばれています。金属類が一切使れていないため、お手入れ次第でとても長持ちし、非常に軽くなっています。※曲物(まげわっぱ)飯櫃や弁当箱などに利用される板を曲げてつくった容器 時代とともに過去のものとなりつつある曲物ですが、近年その良さが見直され、愛用する方が増えてきています。 博多曲物 玉樹 多の町で400年以上の長きにわたって博多曲物を作り、伝えてきた柴田家。 その十八代目として家業を継ぐのが女性であり、母であり、職人である柴田玉樹(本名:真理子)。 十八代目 柴田玉樹 柴田家の十八代目曲物師として活躍。工房で曲物を制作するかたわら、福岡の伝統文化を伝える「博多町家ふるさと館」の 実演コーナーにて毎週木曜日、曲物の制作の様子を一般の方々に向けて伝えています。 標準語が博多弁という、根っからの博多っ子です。 博多曲物」一筋300年 博多の筥崎八幡宮は、大分の宇佐八幡、京都の石清水八幡宮と並び日本三大八幡と呼ばれ、広く崇敬を集める大社です。その西にある門前町のひとつ馬出で昔、応神天皇ご誕生の際、胞衣箱として奉納された故事から曲げ物作りが始まりました。やがて庶民にも親しまれ、江戸時代には貝原益軒の「筑前国続 風土記」で紹介されるほどとなり、三百年の伝統を誇っています。柴田徳五郎司は福岡市無形文化財の指定を受け、博多曲物の職 人技として広く市民に親しまれ、愛され続けています。筥崎宮近くの馬出で約300年、無形文化財である「博多曲物」を伝えてきました。
残り 1 点 6700.00円
(67 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 05月11日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)
-
ラッピング
対応決済方法
- クレジットカード
-

- コンビニ前払い決済
-

- 代金引換
- 商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥299,000 まで対応可能)
- ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
-
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行 - Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)
-